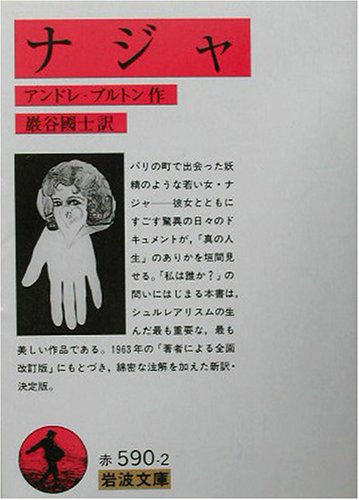アンドレ・ブルトン著 巌谷 國士訳 ナジャ
アンドレ・ブルトン著 巌谷国士訳 ナジャ
まず、訳註の熱量がすごい。これだけ長くても私が最後まで参照しながら読めたというのもすごい。しかし註を先に読むか後で読むかというのは悩ましい問題。
作品の感想を書くのは難しい。見知らぬ大きな家の中で迷ってしまったような感触。根本的に私はこの作品が何を書こうとしたのかが掴めていない。シュルレアリスムの小説と思い込んで読みはじめたせいで余計に迷子になったのかもしれないが、ブルトン自身手探りで書いているのだろうという感じもある。彼はなぜナジャを書いたのだろう?彼女との約束という以外に?もちろん自責の念もあったのだろうが。
作品中に現れる追憶のノスタルジー、鮮烈な思想、時にはっとする切実な呼びかけは美しいが、私にはそれ以上に生の不可解さと虚しさが残る。批判的な意味ではなく。私とは誰か?それは私は誰とつきあっているのかを知ること、といっても私は他者を理解し得ないのだし、やはり自分も理解し得ないのだ。ナジャを掬い上げようとし、自分を掬い上げようとしても、砂のように零れ落ちるのは、本人が最も痛感しているところだろう。しかしそれでも試みた理由は何だったのだろう?
美とは痙攣的なものだろうという結語は様々なイメージを呼ぶが、死と生の狭間を強く想起させるものでもあり、やはりこれはナジャのための言葉なのだろうという気がする。
中上 健次著 枯木灘
中上 健次著 枯木灘
和歌山の枯木灘と呼ばれる土地を舞台に、複雑な地縁と血縁の関係に縛られた青年秋幸をめぐる半自伝的小説。秋幸サーガ三部作の二作目ということなので、本当は一作目の岬から読んだ方がいいのだろうけど、枯木灘単体で読んでも完結はしている。
読む前はもっとラテアメ的な生の豊穣と混沌の世界を勝手に想像していたが、随分印象が違う。血と暴力、生と死、土着性、ポリフォニー、といった構成要素はよく似ているのだが。海と山に閉ざされた枯木灘はその名前のとおり不毛な場所であり、死と新たな生とどちらも描かれてはいるものの、それはあくまで反復に過ぎない。発展し多様にひらかれていく生の可能性、豊穣さとはまた別のものだ。内容の濃密度にも関わらず全体に空虚さが漂っていて、なんだか不気味なものを読んでしまったという感触があるのはここら辺が原因のような気がする。クライマックスを過ぎ秋幸が姿を消しても物語は急激には瓦解せず、秋幸のいた位置に徹が移行し、秋幸の噂ばかりがエコーのように響く終盤は薄気味悪いものがあった。個が消えても関係の網目は回復され、土地の生活は依然として続いていく。空虚といえば、枯木灘は個人的にあまり色彩を感じない作品だったが(色というより透明感、光の陰影の印象)、白は妙に印象的だった。ユキの白粉、紀子の白い体、美恵の白い顔、白痴の子、夏芙蓉の花。
それともうひとつ印象的だったのは文体。内容に反して静かな、どことなく清潔さを感じる文章だが、〜た、で終わる短文がとても多い。おかげで一文ごとに息が切れるような感じを受けるのだけど、そのリズムは秋幸の息苦しさ、切迫感そのものだ。読みやすさ、滑らかさという点では決して名文ではないけれども、忘れがたい文体だった。
J.D.サリンジャー著 村上 春樹訳 キャッチャー・イン・ザ・ライ
J.D.サリンジャー著 村上 春樹訳 キャッチャー・イン・ザ・ライ
十数年振りに訳を変えて再読。春樹訳は大分マイルドで読みやすい感じ。再読といっても細かいことは全然覚えてなかったのでほぼ初読といっていいぐらい。
青春小説の常として、十代の頃に読んでれば〜という感想をよく見かけるが、個人的には読んだ当時はむちゃくちゃ共感したとかそういう記憶はなかった。まあ私はもともと日和見主義だし、ホールデンの言うインチキ側の人間だという自覚はなくもないので逆に耳が痛い方だったかもしれない。
むしろホールデンと大分歳が離れた今の方が目線が違うから感じるものが増えた気がする。ホールデンの、大人になりたいけどなりたくない、子どもと大人、自分と他者の境界線上でバランスを崩して今にも転落しそうな危うさ、インチキに反発しながら彼自身純真な子どものままではいられない矛盾。大人になるということは、子ども時代の全能感、自分の閉じていた天動説的な世界を崩し、他者(とその世界)を受け入れ尊重することを求められるということだけど、ホールデンはその過程で大分混乱してしまっている。多分ロールモデルが見つからないのだ。一方で、終わりつつある子どもの世界、ライ麦畑は美しい。ライ麦畑で捕まえたい、捕まえてほしいのは彼自身のことでもあるだろう。その混乱の原因は、彼がインチキ=表面的にではなく本心から誰かと繋がりたい、受け入れたい、受け入れられたいという望みを持っているからこそではあるのだけれども。
でも、終盤フィービーに一緒に連れてってと懇願された時、彼もやはり大人側の対応を取らざるを得ない。子ども時代は否応なしにいつかは終わる、ライ麦畑からいつかは落ちる時が来る。しかし落ちたらそれで終わりというわけじゃなく、拾ってくれる人は恐らくいるのだし、その可能性は何度も示唆されている。そしてホールデンも少なくともこの語りの時点では生き延びた。そう思うと、彼の語りは痛快なところもある半面なかなか苛だたしいところもあるのだが、最後にはちょっと愛おしい気持ちになる。私も歳をとったなあ。
ルイ=フェルディナン・セリーヌ著 生田耕作訳 夜の果てへの旅
ルイ=フェルディナン・セリーヌ著 生田耕作訳 夜の果てへの旅
様々な物議をかもした問題作家セリーヌによる、青年医師フェルディナン・バルダミュの幻滅に満ちた遍歴を描く半自伝的小説。
やたらと辛そうな前評判、独特かつ饒舌な文体、上下二巻本、これは確実に苦行と覚悟していたところ、案外没入して読んだ。基本のトーンは陰惨だが、ユーモアはむしろよくきいているし、時に詩的なフレーズが浮かび上がる、波のような呼吸のような文体は一度慣れると癖になる。世界への呪詛と評される作品であり、確かに一言で表そうとすればそうなるのだけれども、実際のところ呪詛という程には攻撃性も残酷さも(二人の)フェルディナンには感じない。人生の不毛さ、人間の醜悪さというテーマであればもっと一撃必殺でぐっさり刺しにくる作品は他にもあるが、この夜の果てへの旅の最後に待っていたのは泥のような疲弊感とそれでも否応なしにやってくる次の朝を受け入れるしかない奇妙に明るい諦観だった。
主人公バルダミュは基本的に傍観者であり、何か目指すところがあるでもなく腐敗と破滅からの逃亡を繰り返すうちに、最後に悪友ロバンソンの死によってついに沈黙に至りつく。バルダミュと対照的に良くも悪くも(大概悪い方な気がするが)行動的なロバンソン、彼らは腐れ縁というには運命的すぎる表裏一体の存在であり、ロバンソンの死は同時にバルダミュの語りの息の根を止める。これまで長々と彼の饒舌すぎる語りを追ってきた読者にとって、最後の「もう何も言うことはない」の一文は劇的だ。物語の最後としてある意味これ以上ストレートな終わり方はないのだけれど。しかしこのふっつり途切れるような終わり方は、最後に旅の続きが自分に引き継がれたような感覚を残す。それが読了後に感じる謎の明るさの一因のように思う。
アゴタ・クリストフ著 堀茂樹訳 悪童日記

- 作者: アゴタクリストフ,Agota Kristof,堀茂樹
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2001/05/01
- メディア: 文庫
- 購入: 100人 クリック: 3,630回
- この商品を含むブログ (276件) を見る
傑作と聞きつつもなんやかやで後回しにしている作品はたくさんあるが、たいがいは実際に読むと確かに傑作でしたすみませんでしたとなるもので、この「悪童日記」もまさにそんな作品だった。これは傑作だ。今更私に言われるまでもないのだが。
戦争による生活難から母に連れられ「大きな町」から「小さな町」のおばあちゃんの家に預けられた双子の男の子たち。働かざる者食うべからず、ということでどケチで口の悪いおばあちゃんのもとで彼らは仕事をし、その他生きるための奇妙な独自の練習を行い、下宿人や町の人達と交流する日々をノートに記す。その日記がこの作品という体裁だ。
まず特異なのはその文体で、この日記自体が彼らの奇妙な練習の一つなのだが、彼らはそこに客観的な真実以外を書かないというルールを持ち込んだ。そのため、日記であるにもかかわらず彼らの感情・主観的意見は一切書かれない(彼らの行為や言葉からある程度のことは推し量れるのだが)。あまりにクリアなレンズでパンフォーカスに世界を見ている感覚。このレンズを通してみると、戦争という限界状態の中で起こる悲惨な出来事や生々しい欲望もある程度すんなりと飲み込めてしまう。はじめは正直この文体のおかげでちょっと助かったと思っていたけれど、これは恐ろしいことでもある。書くという行為は世界を読むという行為だということを思い出す。逆もまた。その点では、この日記は確かに生きるための練習なのかもしれない。
しかし、じゃあ無味乾燥な文章かというと全くそんなこともなく、シニカルでブラックなユーモアがそこかしこにひそみ、簡素な描写から各キャラクターを多面的に彫り込む様は非常に鮮やか。特にアンファン・テリブルたる双子の強かな生き様は痛快ですらある。起きている出来事は悲惨なのに、読み物としてとてもおもしろい。後ろめたい位に。あっという間に読んでしまった。
M.バルガス=リョサ著 木村榮一訳 緑の家
ペルーの密林と砂漠を舞台に、複数の物語が時系列もばらばらに目まぐるしく切り替わりながら縦横無尽に展開していく。ピウラの町の外れ、砂漠に建てられた娼家「緑の家」の興亡と元「緑の家」の主のその後、密林からシスター達の伝道所に連れてこられたインディオの娘の身の行方、かつては密林でインディオ達を統率し強盗団のボスとして略奪に明け暮れていたが今は病の身を船上に横たえる日本人の過去の回想、ピウラの町ののらくら者の番長達。どのピースをとっても豊穣で面白い。マジックのつかないリアリズムでもこの面白さ、ラテアメはすごいな…。
登場人物の呼び方が時と場合によって変わる上、現在と過去の回想がシームレスに語られるので最初はちょっと読みづらいが、いったん慣れるとぐいぐい物語に引っ張られていく。文体自体は平明で会話文が多いし、むしろ乗ってくると読みやすい。上下二冊でおまけにそれぞれ結構な分厚さではあるが最後までだれることなく読まされた。読者に能動的な読み方を促すけれど、それが鼻につくこともなく、むしろ一緒にピースをはめていくのが楽しい作品。暴力と悲惨に溢れた物語ではあるし、読んでいて多々辛いところもあったけれど、その混沌を否定するのは難しい。根底にあるのは善悪含めた生への肯定なのだろう。
伊藤 計劃 ハーモニー
伊藤 計劃 ハーモニー
「大災禍」という世界的危機以降、人類は人命・健康を何よりも優先し病気のないユートピアを築き上げた。善意に溢れたというよりも善意しか許されない、個々人の生命は社会的リソースとして大事にされる社会で自殺を選んだ三人の少女。うち実際に死んだのは一人だけだったはずだった。生き残ったうちの一人、霧慧トァンは再度世界を襲う謎の危機に死んだはずの少女が絡んでいることに気づく。ユートピアの到達点のその向こうを描くSF。
ようやく伊藤計劃を読んだけれども、これは読んでよかった。やっぱり意識がテーマとして絡んでくるSFは好き。意識の価値を問うという点ではブラインドサイトを思い出すけれど、ハーモニーの(物語的に)おもしろい点は人類社会の到達点の一つとして人類自身がこの問題を提示し選択するところだなあ。あとがきインタビューで本人も言っていた通り、ロジックをベースに色々乗せて作品を作っている感じで、全体に淡々とした印象がありするっと読んでしまいそうになるけれど、展開も結末もなかなかにドラスティックだ。読了後色々と思考がまとまらなかった。三人の互いへの思いも、考え出すときりがない。